- ビジネスに関する時事情報
- デジタル化・IT化によるビジネスの自動化・効率化
- ホームページ作成
- ビジネス効率化に有効な情報機器の紹介
- デジタルマーケティング
- ロボット・IoT・AI (人工知能)・その他
【運営元】株式会社ダークマター
【その他】プライバシーポリシー

サイバー攻撃の手法は日々進化しており、その中でも「ボイスフィッシング」と呼ばれる詐欺が企業に深刻なリスクをもたらしています。これは特定の階層(経営層や現場担当者)に限らず、あらゆる立場の従業員が標的になりうる攻撃です。
ただし、企業を守る上で、経営層がこの脅威を正しく理解し、方針を示すことは極めて重要です。本記事では、ボイスフィッシングの概要と、企業全体でリスクを低減するための経営的なアプローチをご紹介します。
ボイスフィッシングは、攻撃者が電話を使って企業や金融機関などになりすまし、個人情報や認証情報を引き出そうとする手口です。近年ではAI音声を使った「なりすまし」も登場し、従来よりも信ぴょう性の高い詐欺が行われるようになっています。
特に注目すべきは、AIによる音声合成技術の進化です。たった数秒の音声サンプルから、特定人物の声をリアルに再現できるツールが一般にも出回っており、これを悪用すれば以下のような攻撃が可能になります:
実在の上司・役員になりすました電話指示
顧客や取引先の声を装って契約情報を引き出す
社内音声チャットや留守電を使った指示偽装
このような音声合成技術は、以前はハイエンドな研究用途が主でしたが、現在はオープンソース化・商用化が進み、誰でも手軽に悪用できる環境が整いつつあるのが現実です。
ボイスフィッシングは、ITシステムの脆弱性ではなく 「人間の判断ミス」 を突く攻撃です。どれだけ堅牢なセキュリティシステムを導入していても、電話1本で情報が漏えいする可能性があります。
また、リモートワークや外部委託の拡大により、「声だけのやり取り」が以前より一般的になった今、このリスクはさらに高まっています。
1. 情報セキュリティに対する明確な姿勢の表明
トップがセキュリティを「経営課題」として捉え、方針を明示することで、全社的な意識と行動の変化が生まれます。
2. 全従業員向けの実践的な教育機会の整備
特定の部門だけでなく、営業・経理・総務・コールセンターなど、日常的に外部とやりとりを行う部門に対する教育は特に重要です。
3. なりすましへの確認ルールの徹底
重要な依頼や情報提供が電話で来た場合には、「一旦切って、正規のルートから折り返す」といったプロトコルを社内規則として明文化しましょう。
音声なりすましのような技術的リスクは、表面上は高度であっても、突破口は意外とシンプルな「電話での一言」から始まります。だからこそ、人の判断に依存するリスクを前提とした組織設計と教育が求められています。
セキュリティはIT部門だけの課題ではなく、企業文化として経営層がリードすべき領域です。技術が進化する今だからこそ、組織としての「基本動作」を再点検してみてはいかがでしょうか。
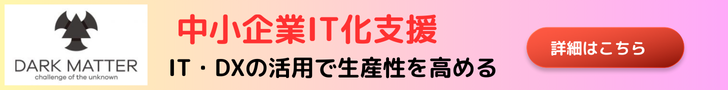
👇このページのQRコード
【運営元】株式会社ダークマター
【その他】プライバシーポリシー